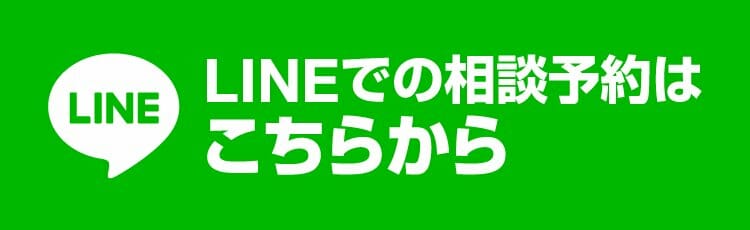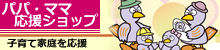目次
ハザードマップの種類
ハザードマップといわれるものには一般的に以下の種類がございます。
・水害ハザードマップ
・内水ハザードマップ
・土砂災害ハザードマップ
・地震防災マップ
不動産探しで良く気にされるハザードマップは?
当然すべてのハザードマップが重要なのですが、特にお客様からよく言われるのが「洪水ハザードマップ」「内水ハザードマップ」の2種類を気にされる方が多い傾向です。
洪水ハザードマップにおける不動産会社の知識不足

法で重要事項説明での説明義務が課せられているにも関わらず、ハザードマップ上の物件の場所だけを説明し具体的な内容を把握していない不動産会社・営業マンが多いのが現状です。
果たしてそんな会社の重要事項の説明が本当に正しいものなのでしょうか?
弊社が経験した他社(営業マン)の例を挙げて解説します。
洪水ハザードマップは1000年に一度の大雨を基に作成しています。
間違い
「想定最大規模」の降雨規模は1000年に1 回程度を想定していますが、正しくは1000 年毎に1回発生する周期的な降雨ではなく、1年の間に発生する確率が 1/1000(0.1%)以下の降雨です。(国土交通省にて最大外力(想定最大規模)の設定方法が決まっております)
ちなみに1/1000の確率は10回コイントスをして10回ともに表(裏)が出る確率が1/1024となります。
重要事項説明書の内水ハザードマップの有無のチェック欄にありとしている。
間違い
各市区町村毎に内水ハザードマップを作製している為、ありとチェックしている会社が多々ありますが、その項目の最上部に「水防法に基づく水害ハザードマップにおける当該宅地の所在地」と書かれているはずです。
さいたま市を例に挙げると市のホームページの「さいたま市内水ハザードマップについて」に「水防法施行規則の規定に基づくものではありません」と明記されております。
なので、無しにチェックが正解です。
古いハザードマップを使用している
間違い
というより論外です。更新頻度の明確な規定はないのですが・・・さいたま市においては令和7年1月にハザードマップが更新されております。
当然、治水設備の整備や街の再開発状況によって「想定最大規模」は変わってまいりますので最新のものを使って説明しないと何の意味もない説明となります。
なぜこのようなことが起きるのか?とあくまで推測になりますが、ハザードマップは役所で無料交付しているものであり、複数冊(枚)ストックしており機械的に渡しているからだと思います。
不動産会社(営業マン)だから不動産のプロではない。

ここまでの内容でお気づきの方が多いと思いますが・・・
不動産会社だから不動産営業だから宅建士だから不動産のプロというわけではありません。
ハザードだけでなく、これから太陽光パネル搭載の建売住宅もどんどん増えてきます。
太陽光の発電のイメージは、大半の方が「日が多い夏」と答えると思います。営業マンからも「エアコンを使う(電気代が高くなる時期)夏に一番発電する」といったことを言われておりませんか?
これは大きな間違いで実は太陽光パネルの性能を示す時は、測定時モジュールの温度が25度であることが国際的に定められた条件となっており、日本では4月~6月が一番性能を発揮するといわれております。
耐震等級に関しても同じです。「耐震等級3だから大きな地震が来ても倒壊しないので安心です。」も残念ながら間違いです。
建築基準法では「新築住宅に係る各等級に要求される水準は,極めて稀に発生する地震による力に,等級に応じて少なくとも各規準の倍率を乗じて得た数値となる力の作用に対し,構造躯体が倒壊,崩壊等しないこととする。」(国土交通省HP評価方法の基準 11ページ記載)とされており損壊し始めることや損壊をし始めた建物が複数回の地震(大きな余震)に対して倒壊や崩壊することは規定されておりません。
事実として言えることと言えば、直近で大きな地震があった熊本地震の被害では、耐震等級3の建物への被害が少ない傾向です。国土交通省の『「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会」報告書のポイント』の資料によると、等級3の被害は、以下のように報告されています。
無被害…87.5%
軽微・小破…12.5%
倒壊はゼロで、80%以上の建物が、無被害ですが耐震等級3でも軽微・小破は12.5%もあったということです。
NextStepではお客様に正確な情報をお伝えいたします。
弊社では、「弊社にとって都合の良い解釈」や「お客様にとって都合の良い解釈」で物件の良し悪しをお伝え致しません。
何故なら「良いことだけを伝えて、万が一の事があったとき責任を取ることが出来ないから」です。
不動産には必ず「メリット」「デメリット」があり「デメリットを理解した上で、そのデメリットを上回るメリットがある」物件が最良の物件だからです。
まずは下記フォーム・LINEよりお気軽にお申し付けください。
ご希望の条件沿った物件のご提案、メリット・デメリットのご説明をさせていただきます。

 お気に入り
お気に入り