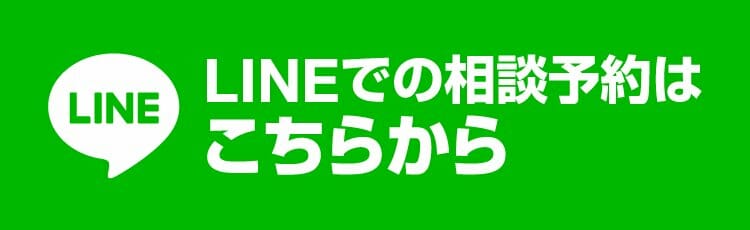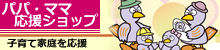目次
10年前の水準に戻った変動金利

大手銀行5行は3月31日、4月の住宅ローン金利を発表しました。契約者の7割超が選択している変動型について、全行が基準金利を0.25%引き上げ、2.875%(前月2.625%)となります。日銀の追加利上げを受け、変動型の指標となる短期プライムレートを3月に引き上げたことを踏まえた。みずほ銀行は新規借り入れのみ基準金利を2.625%(同2.475%)としました。
最優遇適用金利(実際の最優遇借入金利)は?
適用金利は基準金利から顧客の信用力に応じた優遇幅を差し引いて決定します。変動型の新規借り入れの最優遇金利は、三菱UFJ銀行が0.595%、三井住友信託銀行が0.73%、りそな銀行が0.64%と、いずれも前月から0.25%引き上げました。三井住友銀行は0.925%と0.3%引き上げ、みずほ銀行は0.525%と0.15%引き上げました。
ネット銀行の変動金利(最優遇適用金利)はどうなってるの?
金利が低いとされているネット銀行の金利はどうなったのでしょうか?
①PayPay銀行:0.780%
②SBI新生銀行:0.410%
③イオン銀行:0.780%
④住信ネットSBI銀行:0.698%(物件価格の80%融資)80%超えの場合は0.948%
⑤Auじぶん銀行:一般団信の場合0.73%(物件価格の80%融資)80%超えの場合は0.775%
⑥ソニー銀行:0.547%(物件価格100%(100%以上の場合は0.05%上乗せ)・各種ZEH、認定長期優良住宅をはじめとする環境配慮型住宅の新築物件の購入・新築の場合)その他の場合は0.647%(物件価格100%(100%以上の場合は0.05%上乗せ))
と軒並み上昇しております。
0.25%上昇で月々の負担はどれくらい上がるのか?
仮に4,000万円の物件に諸費用200万円の総額4,200万円を35年の変動金利、ボーナス支払い無しで住宅ローンで組んだ場合のシュミレーションをしてみましょう
4,200万円・35年・変動金利0.39%の場合
月々支払額:106,996円
4,200万円・35年・変動金利0.64%(0.25%上昇)の場合
月々支払額:111,644円
となり
月々4,648円の支払額(負担額)増
となります。
今後の金利の見通しは?

まず大前提として「変動金利の基準金利は日銀の政策金利と比例する」という事を念頭に説明してまいります。
日銀は「どの程度まで政策金利を引き上げるつもりなのか」ということが重要である。3月の決定会合で据え置いた0.5%という政策金利について、植田総裁は「まだ上げる余地がある」と認識している模様で現状を「まだ金融緩和の状態」と見ているわけである。
今後の焦点になるのは「植田総裁は中立金利(※)をどの程度の水準と考えているのか」だろう。
※「中立金利」とは、政策金利が「金融緩和」的でも「金融引き締め」的でもなく、経済や物価などの情勢に対して「中立」である状態を指す。
植田総裁は、「何%が中立金利」と具体的に表明しているわけではない。ただ「中立金利というものがあるとして、それが一定と決まっているなら、それに到達するまでは利上げを続ける」との考えを明らかにしている。また、日本銀行が2024年8月に公表したワーキングペーパー (論文) によって「日本銀行が掲げる2%のインフレ目標を前提にすれば中立金利は1~2.5%」との見方が浮上した。簡単にいえば「少なくとも金利が1%に到達するまでは追加利上げが行われる可能性がある」ということです。
上記の事から、変動金利は4月の金利よりさらに0.5%程度上昇する可能性があるという事になります。
さらに0.5%金利が上昇したらどうなるの?
先程と同じく4,000万円の物件に諸費用200万円の総額4,200万円を35年の変動金利、ボーナス支払い無しで住宅ローンで組んだ場合のシュミレーションをしてみましょう。
4,200万円・35年・変動金利0.39%の場合
月々支払額:106,996円
4,200万円・35年・変動金利1.14%(当初より0.75%上昇)の場合
月々支払額:121,320円
となり0.39%で借入を行った時より
月々14,324円の支払額(負担額)増
となり、
4月以降の借入を行った方であれば当初より0.5%増となりますので
月々9,676円の支払額(負担額)増
となります。
影響は月々の負担増だけ?
これはお借入れされる金融機関によっても異なってまいりますでの何とも言えないのが現状ですが・・・
当然金融機関によって審査内容が異なります。
その中で一番影響が出ると思われる部分が審査金利が増えるという事です。
住宅ローンの審査では一般的に借入金利(実行金利)と異なる金利で審査を行う金融機関が多いですが、一部の金融機関では借入金利(実行金利)で審査する金融機関も御座います。
解りやすく説明すると
A銀行では審査金利が3.3%、B銀行では0.6%(実行金利)で審査するという事で、同じ借入金額であれば当然後者の方が年収に対しての返済負担率が低くなります。
という事は
同じ年収であればB銀行の方が多く借入可能という事となります。
B銀行のように実行金利で審査する金融機関を利用しても実行金利が上がれば当然借入上限額は減る形となりますし、資材や地価の高騰や人件費の高騰で物件価格が上がってきている中では購入できる物件に制限が出てくるという事になります。
不動産の買い時は?
筆者は預言者でも未来からタイムトラベルしてきた人間でもないので不確定な未来に関して断言は出来ないのですが・・・
住宅価格(物件価格)について
国産材割合が4割を切っている住宅建材市場ですから為替相場の影響もあると思いますが、材料は輸入材でも国内で製造されている製品も多く、昨今の人件費高騰による製造・販売コスト上昇や職人不足(40年で1/3に減少)の影響による職人単価(人件費)の高騰で住宅価格は上昇すると思われます。
金利について
少なくとも現在の植田総裁の任期が2028年4月7日迄ですから「中立金利である1%程度まで政策金利は上がる」と考えておいた方が良いと思います。
トランプ米大統領が2日(日本時間3日)発表した相互関税などを踏まえた日本銀行の金融政策運営について、想定よりも内容が厳しく日本経済に深刻な影響が及ぶ可能性があるとし、追加利上げの時期は先送りされるとの見方がエコノミストの間で広がっている。
上記2点踏まえお答えいたしますと「7月・9月の会合における政策金利の動向を注視し5年ルールや125%ルールのある金融機関で月々の支払額に余裕を持ったローンを組む」方が良いのではないかと考えます。
まとめ
・これからも金利は上昇する可能性は高い。
・金利上昇は月々の返済額だけでなく、借入可能額にも影響する。
・物件価格は上昇していくと思われる。
・購入を検討しているなら、7月・9月会合における政策金利の見直しの状況を注視し5年ルール125%ルールを設けている金融機関で余裕をもったローンを組む方が良い。
不動産に関する事なら下記フォーム・公式Lineよりお気軽にご相談ください

 お気に入り
お気に入り